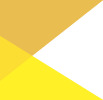猪居亜美インタビュー!(2)音大からデビューまで

こんにちは!生田Pです。今回は9月20日の「名古屋ギターフェスティバル2025」と翌日の「Master Class &Lecture」に出演する猪居亜美さんにインタビュー第2弾です!第1弾はこちら!
公演チラシはこちら!

いよいよクラシックギタリストを決意し、音楽大学へ。
(前回の続き)–それから音楽大学へ入って学んでいったわけだね。じゃあそれまではお父さんのレッスンをずっと受けていたと訳だけど大学に入ると先生も変わってレッスンの雰囲気は変わったの?
そうですね。父親のレッスンはもう「ここガーンとフォルテや!ここはもっと歌って!」みたいな表現優先のレッスンだったんです。私も言うこと聞いて「そんならここはフォルテいったろかな。歌うってこんな感じかな?」みたいな感じで結構直感的に演奏してました。
–そういうレッスンもいいよね、長○監督的な。自分も一回イギリスで巨匠のレッスン受けた時に結構アナリーゼ(楽曲分析)して臨んだんだけど「そうそう、ここはタッタタッタ、キャンキャンと軽めに、アレだ、ミッキーマウスマーチみたいなノリが無いとアカンで(謎に関西弁風)」みたいな感じだったことある。もちろんしっかり勉強することは大事なんだけどそればかりだと感情が薄っぺらくなってしまう感じがしてたから腑に落ちた覚えがある。
そうそう、直感的なレッスンもある程度やっぱり大事なんですよね。私の場合若い頃にたくさんそういった経験ができたので感覚的な面はしっかり自分に馴染んでました。その後大学では藤井敬吾先生や福田進一先生のレッスンに変わって、大学生になったこともあり「なぜここは強く弾くのか、どう展開して解決していくのか、この音はこう言う役割があるからどのように良いのか」と言う感じに考えていかないといけないレッスンに切り替わっていきましたね。それと同時に「あの頃父親にガーンとか言われたことはこういうことやったんや!」とハッと気づくことも多かったです。結果的にバランスよく学ぶことができました。
–確かに音大入ると学ぶことが重要になるよね。バランスといえばレパートリーも自分の好きなジャンルだけでなくバロック~古典~現代まで、理論的なことも含めしっかり広く勉強するから取り組み方も変わるよね?
そうですね、大学入る前はどちらかと言うとコンクール出るために必要な曲を選曲してやることが多かったです。あと課題曲とか、地力をつけるための古典の曲も沢山やってました。大学入ってからはルネサンス・バロックから現代まで曲の時代のバランスも考えながら自分からプログラムとかもある程度決めるようになりました。あと理論や歴史の勉強もあるんで実際にギターを弾く時間のバランスも考えて練習の質もやはり変わっていきましたね。曲による音楽の形式の違いとかも理解するようになったのも音楽大学がきっかけですね。やはり自分で決めることで自発性が出てきて考えながらレパートリーを組み立てていくことが少しづつできるようになりました。
–本当に自発的にプログラムを決めるのって大事ですよね。ではそしてそこから大学で色々なことを学んでギタリストとしてデビューしていくことになったと思うんだけど、「プロになる!」って強く意識したのはいつ?
ギタリストになるにはいかに自分を見てもらうかが鍵
それこそ大学2回生(2年生)の頃にはギタリストになることを結構強く意識していてYouTubeに動画を出したりするようになりました。まだその頃は多分YouTuberとかそう言う言葉もあんまり聞かないくらいの時代だったんですけど、動画での活動を続けていたら今のレーベルfontecのマネージャーさんがそれを見つけてくれて在学中の間にデビューできました。
–確かにまず見てもらえないと何もできないもんね。だいぶ早くに活動を開始したことが功を奏して今の成功に繋がったわけだね。そういえばNGF繋がりで以前来日したクピンスキーデュオも同じような考えを持って活動してたみたいだよ。音楽家としてのキャリア形成って色々やり方あるけどその辺の話もNGF翌日のイベントで伺えるのを楽しみにしてます!
–ではここから今回のNGFで猪居亜美の演奏の見どころ、聴きどころを教えてもらえますか?
今回のNGF会場について
そういえば今回のコンサートは電気文化会館ですよね?めっちゃええホールとして噂は聞いているんで緊張しつつもすごく楽しみにしています。実際どんな感じなんですか?
–電気文化会館は壁面が大理石でとにかく良く響いて、客席で聴くと音が上から降ってくるような感じだね。クラシックギターのいいところをブーストしてくれるような素晴らしいホールだね。全国のホールの中でもクラシックギターとの相性は随一だと思うよ。

バッハとイングヴェイについて
–そして今回はプログラムはバッハからイングヴェイまで(B to Y)ということでこのプログラムは亜美ちゃんならではという感じだよね。バッハもイングヴェイもがっつりと聴かせてもらえるのを楽しみにしてる。ではまずバッハの聴きどころから教えてもらってもいいかな?
実はバッハはこれまで本腰を入れてしっかり取り組むことはしていなかったんです。今年東京での他公演「B to C」もあって「そろそろやってみるか」みたいな感じだったんです。バッハはやはりメロディーが多声的になっているのでそれらを全て聴きながら弾いていくのでなんか弾いていくとついついキャパオーバーしやすいんですよね。
–-麻婆豆腐作りながら同時にタコス作るみたいな?
あ、はい(困惑)。多分そんな感じやと思います。
それでまあ、それをしっかり考えながら練習していくことにして、でもやっぱり中途半端になるのが嫌で突き詰めすぎるとめっちゃ難しくなっていくし、ちょっと困ってたんですよ。でもある日ギタリストの益田展行さんと話してて「構造がそもそも美しく作られているから肩肘張りすぎずシンプルに弾いてみたら?」って助言をいただいて、それから段々とその素朴な魅力に気づきはじめて、モチーフとかも「ここめっちゃ綺麗なメロディーやん」とかなってきました。色々私自身もバッハに魅了されてきてて、最終的にはその簡素なところに最高の美しさがあるような気がしています。聴いた方に「ああ、ここええなあ、素敵やな」って自然に感じてもらえるような演奏ができるといいなと思います。
–バッハの音楽って結構短いフレーズを取り出してみてもやはりそれとなくバッハとわかる普遍的な美しさがあるよね。とても楽しみです。さてあと気になるのはイングヴェイですよ。
イングヴェイって多分クラシックギターのファンの皆様には馴染みがないと思いますのでこちらでご紹介します。
イングヴェイ・マルムスティーン(Yngwie Malmsteen)はスウェーデン出身のギタリスト。1963年生まれ。少年時代は甘やかされて育ったため粗暴な少年で不登校気味。学校に行かずに家でギターの練習をする生活を許され、自宅でひたすらギターの練習に費やし、神童のごとくギターが弾けるようになっていく。幼少期からクラシックも聴いていたのでそういったフレーズをギターでも弾いてみたりとギターや音楽への興味は向くが生活面では「学校の廊下をバイクで走る」など素行不良で15歳で学校を退学。ギターの才能を認められ、なんと20歳の時にヘヴィメタルバンドのアルカトラスのギタリストとして一躍有名になり、以後ロックにクラシック要素を織り交ぜたプレイスタイルを確立し、ギタリストとしての名声を得た。なお身長は190cm。服装は黒い革ジャンに黒い革パンツ、そして胸はいつもなぜかはだけている。王様。
簡単イングヴェイまとめ
要はヘヴィメタル、ロックギター界のスーパースターです。ちなみにプレイを聴いてみるとかなり洗練されており素行不良な少年感はなく、音も素直で綺麗です。クラシックファンも割と抵抗なく聴けると思います。
–さてそんなイングヴェイのトリロジーなどもこれまた意欲的なプログラムだよね。編曲は自分で?
そうですね。全部自分で編曲しました。フルで弾いて8分くらいなんですけど少しだけ短くしてます。
–なるほど、ちなみにトリロジーはエレキでも弾いてたりしたの?
いや、エレキではそれこそ難しすぎて、ピッキング(ピックを使って弾くこと)とかも全然違いますし、とてもじゃないけど弾けません。エレキでも「イングヴェイ弾けまっせ」って人少ないじゃないですか(笑)。私もその一人でエレキでは流石に無理でした。それもあってクラシックで弾いてます。
–確かに(笑)。自分で「インギー弾けます」ってほぼ居ない気がするね。(なお、生田Pは過去にスティーヴ・ヴァイ派だったが弾けたのはせいぜい数曲)。エレキはまた違った難しさがあるよね。
そうなんです。まあいざ自分でホンマに編曲してみて、クラシックギターで弾いたら「こんなん他に誰が弾くねん!」って感じなんですけどね(笑)。原曲はインストで、ギターももちろん難しいんですけど、ドラムのリズムだったり、そもそも曲の美しい構成だったり、音づかいだったり、そういった魅力が伝わるように弾けるといいなと思っています。
–原曲では中間部は割とクラシックギターでもいけそうだけど、それ以外はエレキギターの掛け合いみたいな感じで、ギターの音色もそれぞれエフェクターかけてあるからフレーズごとに雰囲気違うもんね。それを一本のクラシックギターでエフェクターもアンプも無しで表現するってなかなかのチャレンジだね。亜美ちゃんのテクニックでスパパパッと強烈に切り裂くように速弾きフレーズを弾くのはなんか想像できるかな。それにしても4倍くらいの仕事量だよね。いやあ、これはイングヴェイ本人にも聴きに来て欲しい笑。
「クラシックもロックも弾く」新たなギタリスト像
–最近亜美ちゃんは「クラシックもロックも弾く」という姿勢で最近精力的に活動していると思うけどきちんとリスペクトをしつつジャンルの垣根を越えるということがしっかりできているよね。これはやはりこれまでの音楽遍歴が影響していると思うけどその辺りの感触はどうかな?
この活動の感触はすごくありますね。聴きに来てくださる方も様々で面白いですよ。例えばランディローズの影響でちょっとクラシックギター弾いてみる方もいらっしゃると思いますし、逆にクラシックファンの方もロックを聴いて「ああ、こういう曲もあるんだな」と気づいてもらえることもあったりと相互に作用していてとても面白いことなんじゃないかなと思います。何より自分がいろんな音楽が好きなんでいろんなことにもチャレンジできますし。
–ランディローズはクラシックギターも弾いていたロックギタリストとして有名だよね。左手のフォームなんかもクラシックっぽいし、曲名で紹介するとDeeとか「これクラシックギターの曲やん!」っていうくらい違和感ないもんね。(気になる方は「Dee ozzy osbourne」とかで検索すると出てきます。短い曲ですがなかなか味があっていいですよ。)
そうなんですよ!さっきのバッハもそうですけど音楽の魅力って本質的にはジャンル関係なく、ただ普遍的な美しさだったり、誰もが楽しめることだったりすると思うんです。自分はクラシックギタリストですけど好きなものは幅広いですし、コンサートを聴きに来てもらったりしてそれを知ってもらえることがとても嬉しいです。
–ありがとうございます。ええ話ですやん(泣)。ちなみに今回使うギターは?
今回使うギターは!
マーク・ウシェロビッチのダブルトップです。音量が豊かで音色も好きなので最近のステージではずっとこれを使っています。これですね。
https://x.com/amiinoi/status/1804749315099025620
–ありがとう。世界的にも人気がある製作家だね。ダブルトップとはその名の通り、表面板が薄く2枚構造になっていて、音響性能が格段に上がりますよね。単に2枚重ねてもあまり良い音にはならずボコボコしてしまい、上手に作るのは非常に緻密な作業とセンスが必要なのだけどウシェロビッチは音色に対する理論がしっかりしていて、ダブルトップながら透き通った音のする素晴らしいギターだよね。そんな名機を使用してコンサートホールに響き渡るバッハと、イングヴェイ、めちゃくちゃ面白い!本当に楽しみにしています。
コンサート翌日にはイベントも!
–21日の方の公開レッスンと講座も楽しみにしています。講座では亜美ちゃんの普段の練習のスタンスだったり、音楽家として生きるためのキャリア形成の仕方などのお話を聞けたら嬉しいです。内容は少しこのインタビューと重複することもあると思うけど実際にギターを使ってどんな風に練習するのかなど秘密に迫っていきたいと思います。亜美ちゃん、インタビュー受けてくれてありがとうございました!
ありがとうございました!NGF2025で名古屋の皆様に会えるのを楽しみにしています!
インタビュー(完)
チケットは以下のリンクから!
今回猪居亜美さんが出演する9月20日の「名古屋ギターフェスティバル2025」と翌日の「Master Class &Lecture」のチケットは下記リンクから!(チケット販売サイトSTORESへ)公開レッスンは実際にレッスンを受けていただける受講生も募集しております。